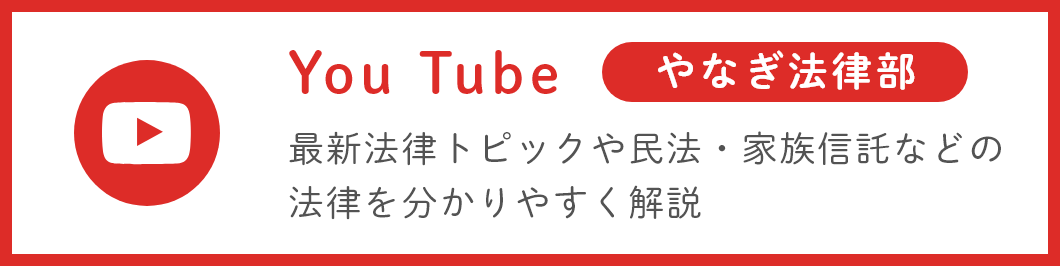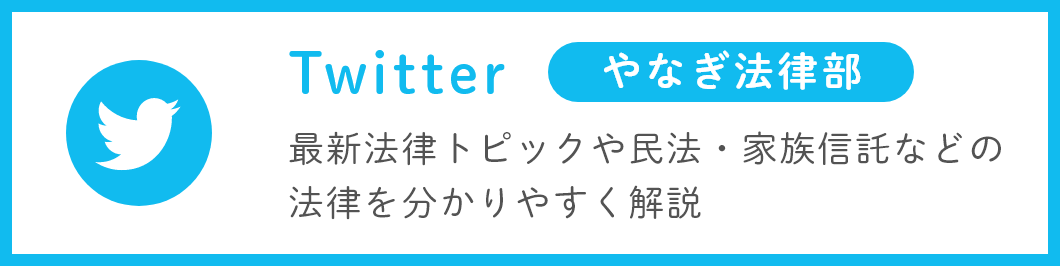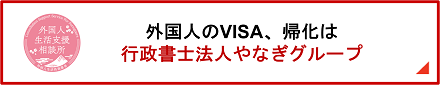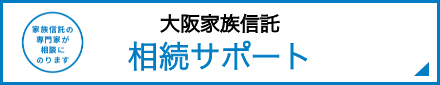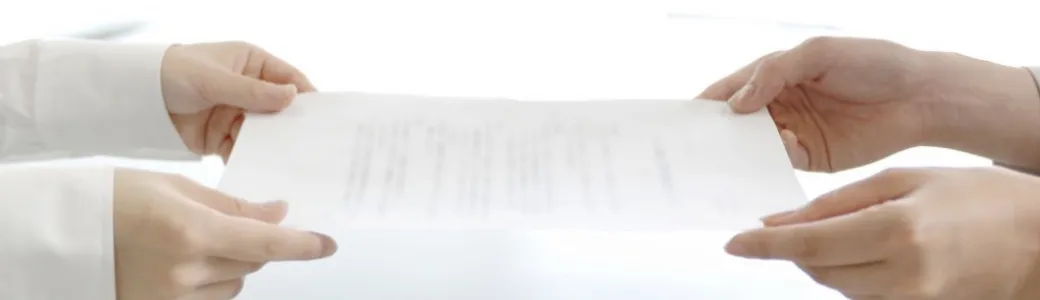
このような方におすすめ
- 相続に自分の意思を反映したい
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(夫)がいる
- 相続人の中に行方不明の人がいる
- 障がいのある子どもに財産を多く渡したい
- ほとんどの財産が不動産
- 家族構成に複雑な事情がある
- 会社の経営を後継者に譲りたい
- 家族や親族の間で相続争いをしてほしくない
- 相続人が一人もいない
- 自分の死後、妻の生活が心配
- 世話になった嫁(婿)がいる
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産がどのくらいあるかわからない
- 家族が知らない隠し子がいる
作成するメリット
不備がなく、確実に遺言を実行できる

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、
内容に不備があると無効になってしまうことがあります。
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、その心配はなく、遺言の内容を確実に執行することができます。
公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のおそれがない
公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されるため、遺言の内容の改ざんや偽造、誤って紛失してしまうような危険がありません。
家庭裁判所の検認が要らず、遺言を速やかに実現
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要となるので、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現することができます。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合を除く)や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対して法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票など必要な書類を提出し、相続人全員が呼び出されて検認の手続きを受ける必要があります。
費用
公正証書遺言作成サポートプラン
| サポート内容 | 相続財産(消却・積極財産を含む) | |||
|---|---|---|---|---|
| ~2,000万円未満 | ~5,000万円未満 | ~1億円未満 | ~2億円未満 | |
| 遺言書作成 相談 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自筆証書遺言 | 98,000円 | 128,000円 | 158,000円 | 個別御見積 |
| 公正証書遺言 ※ | 98,000円 | 128,000円 | 158,000円 | 個別御見積 |
| 秘密証書遺言 | 98,000円 | 128,000円 | 158,000円 | 個別御見積 |
| 遺言保管 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 個別御見積 |
| 検認手続 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 個別御見積 |
| 相続人調査 (戸籍収集) | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 個別御見積 |
| 相続財産調査 (財産目録作成) | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 個別御見積 |
| 遺言執行 (預貯金の名義変更等) | 200,000円~ | 400,000円~ | 600,000円~ | 個別御見積 |
※公正証書証人立会費用(2名) : 20,000円
※この報酬額とは別に消費税及び実費(登録免許税、郵送費、法定手数料等)が加算されます。
※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
- 2無料個別相談
- 事前に財産目録を作成し、遺言の内容を検討しておいてください。
- 3お見積り
- お見積りまではすべて無料です。
- 4ご依頼
- お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
預り金および着手金のお振込み後、委任契約を行います。
- 5資料等の収集
- 必要な資料をそろえていただきます。
- 6当事務所が遺言書の文案を作成いたします。
- お見積りまではすべて無料です。
- 7遺言書文案のご確認
- 遺言書文案の内容を、遺言者ご本人にご確認いただきます。
予め、遺言者および証人の方のご都合をうかがい、確認いただく日時を調整いたします。
- 8公証人との打ち合わせ
- 当事務所から公証人に遺言書文案を送付し、内容について確認をします。
- 9手続きに向けた確認・調整
- 公証人から準備完了の連絡後、公証人に支払う手数料や手続きの日程等を確認します。
- 10公正証書遺言作成
- 予定日時に、遺言者が証人2名と一緒に公証役場に行き、手続きを行います。
よくあるご質問
- 遺書と遺言書はどう違うのですか?
- 遺書とは本人本人の死後、残された遺族のために書き残された手紙です。自分の死を覚悟した人が、伝えたいことやお別れの言葉などを書くことが多く、形式や内容に決まりはありません。一方、遺言書は相続に関する意思を伝えるために書くもので、一定の方式に従って作成する必要があり、法的な効力があります。
- 遺言書の証人は誰に頼めばいいですか?
- 公正証書遺言の作成時には、2名の証人が立ち合う必要があります。未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人は証人になることはできないため、それ以外の親族や友人・知人から信頼できる人を選ぶことになります。司法書士、行政書士、弁護士などの専門家も証人になることができます。
- 公正証書遺言の作成サポートを、専門家に依頼するメリットは?
- 遺言書は自分の意思を伝えるだけではなく、法的な形式を守り、親族間でトラブルにならない内容を作成することが大切です。専門家の作成サポートでは、希望する遺言を反映した文案作成、必要な書類収集や公正証書作成時の証人も依頼することができます。遺言や相続についてアドバイスを得られるなど、さまざまなメリットがあります。
必要書類
遺言者に関するもの
- 本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)……本籍地のある市区町村役場で取得
- 本人の印鑑証明(発行から3カ月以内)……住所のある市区町村役場で取得
- 本人の住民票(発行から3カ月以内)……住所のある市区町村役場で取得
- 本人の実印
財産を譲り受ける人(受遺者)に関するもの
受遺者が相続人である場合
- 受遺者の戸籍謄本(発行から3カ月以内)……本籍地のある市区町村役場で取得
- 受遺者の住民票(発行から3カ月以内)……本籍地のある市区町村役場で取得
※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要
受遺者が相続人以外の人である場合
- 受遺者の住民票(発行から3カ月以内)……住所のある市区町村役場で取得
証人に関するもの
- 証人2名の氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの
遺言執行者に関するもの
- 氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの
※受遺者や相続人が遺言執行者になる場合は不要
不動産相続に関するもの
- 不動産の登記簿謄本……不動産を管轄している法務局で取得
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書……不動産のある市区町村役場や市税事務所
預貯金、有価証券等の財産相続に関するもの
- 預貯金や有価証券、そのほかの財産の内容が確認できるメモ
- 通帳のコピー(金融機関名や支店名が確認できるもの)