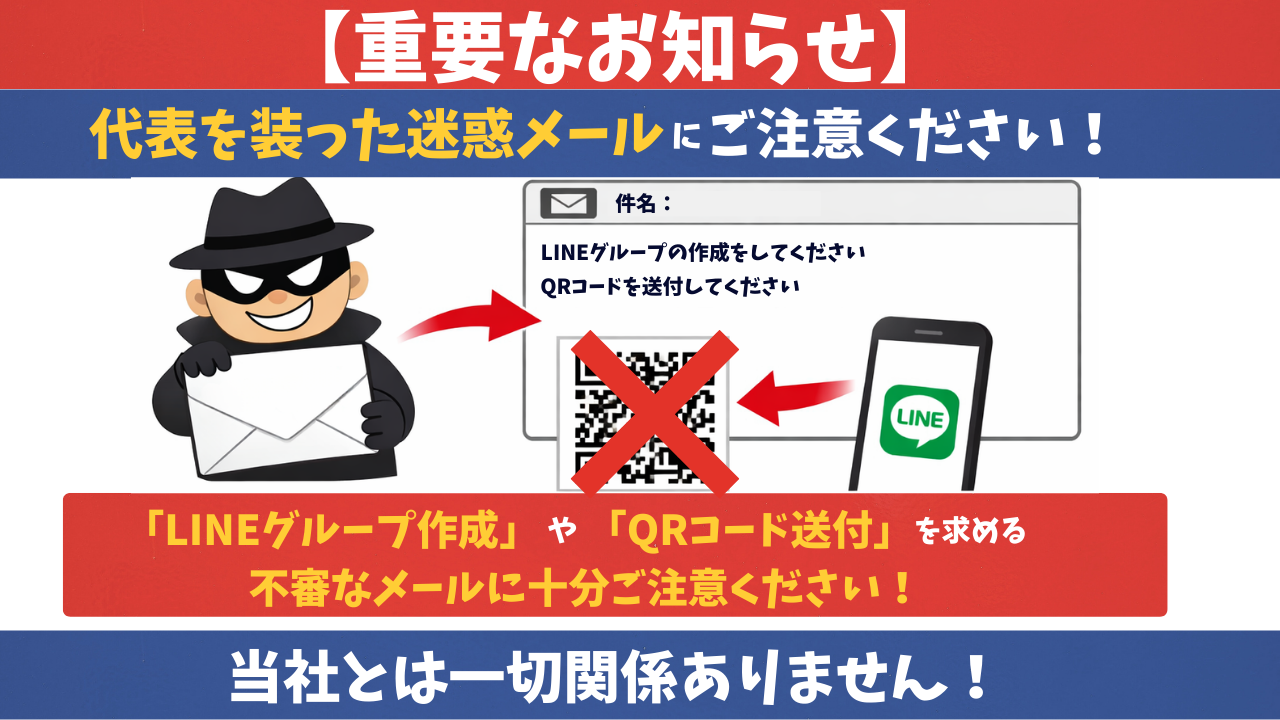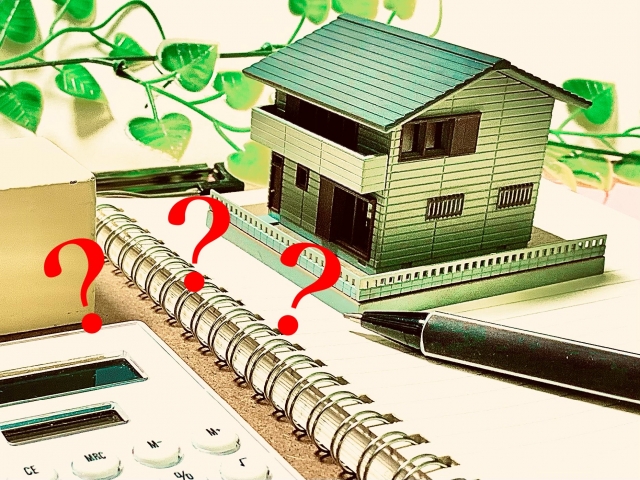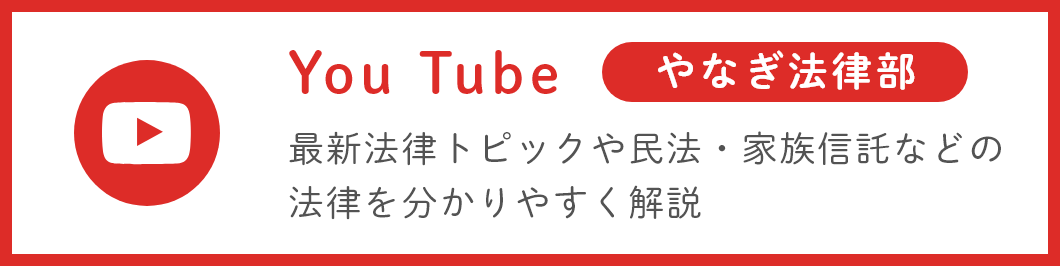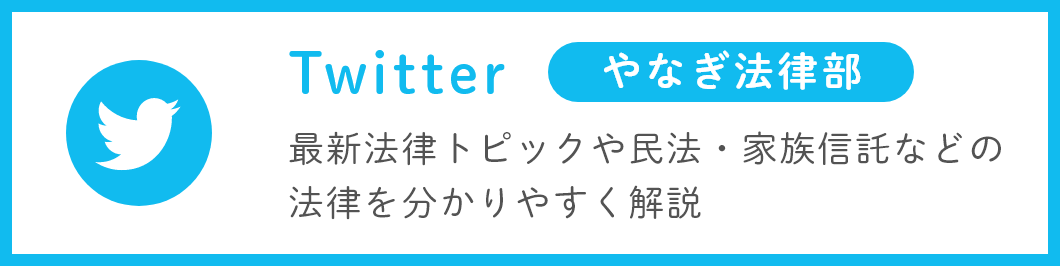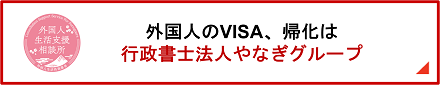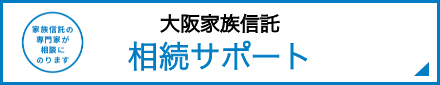春の法改正特集!4月から改正される法律はこれだ!詳しく解説します
この春、相続登記の申請義務化の制度や民法等多くの法律が改正されました。本ブログではこの春に改正される法律についてどのように改正されるかを簡単に説明していきます。どのように法律が改正されか気になる方等は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
1 相続登記の申請義務化について
1-1 相続登記の申請義務化
1-2 相続人申告登記
2 民法の改正について
2-1 懲戒権の見直し
2-2 嫡出推定制度の見直し
3 民事訴訟法の改正について
3-1 口頭弁論をウェブ会議で参加
4 まとめ
相続登記の申請義務化について
相続登記の申請義務化の制度が令和6年4月1日から始まりました。相続登記がまだお済でない方は参考にしていただければ幸いです。
相続登記の申請義務化
・制度全般について
相続人は、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
不動産(土地・建物)を相続で取得した人(相続人)は相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。また、正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続人間における遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産(正しい登記がされていないもの)においても対象となり、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記が必要となります。
詳細につきましては弊所のブログ(https://yanagi-law.jp/blog/5047)をご覧になって頂けると幸いです。
相続人申告登記
相続人申告登記制度は、相続登記の申請義務を簡易な方法で行えるよう新たな登記として令和6年4月1日にスタートしました。詳細につきましては弊所のブログ(https://yanagi-law.jp/blog/5047)をご覧になって頂けると幸いです。
民法の改正について
令和6年4月1日に民法の一部が改正されます。以下では改正される規定のうち懲戒権と嫡出推定制度について説明をしていきます。
懲戒権の見直し
改正前民法822条「懲戒権」の規定が削除されました。懲戒権は、児童虐待の口実に使われることや懲らしめ、戒めるという強力な権利であるとの印象を与え、体罰の正当化の根拠となってしまっていました。そこで改正後民法821条で親権者は子の人格を尊重し、子の年齢や発達程度に配慮しなければならなず、かつ、体罰等の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとしました。また、社会的に許容される正当なしつけは、820条の「監護及び教育」で行うことができるとされています。
嫡出推定制度の見直し
嫡出推定制度とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定すると規定したものです。
しかし、この規定により、離婚をしていても嫡出推定期間内(離婚後300日以内)に生まれた子は前夫の子と扱われるため、母親が出生届を提出せず、その結果、子は無国籍者となっていました。
従前の民法733条では、離婚後100日間(父親の推定重複を避けるため)の再婚を禁止していました(再婚禁止期間)。しかし、前述のような事態が問題視され、嫡出推定規定の見直しが行われました。改正後民法772条では「女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれた子についても、同様(妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する、同条一項前段)とする」とされ、その結果、民法733条の再婚禁止期間が廃止されました。
民事訴訟法の改正について
令和6年3月1日に民事訴訟法の一部が改正されました。以下では改正される規定のうち口頭弁論について説明していきます。
口頭弁論をウェブ会議で参加
民事訴訟において公開の法廷で行われる「口頭弁論」がウェブ会議で参加できるようになりました。
裁判所が当事者の意見を聞いて相当と認めたときは、当事者は裁判所に出頭せずにウェブ会議での参加を希望することができます。
既に「弁論準備手続」や「和解期日」などについてはウェブ会議(映像と音声付の方法)や電話会議ができるようになっていますが、「口頭弁論」の場合、法廷にモニターを設置し映像の送受信のみとなります。カメラ機能を有効にした状態での参加です。また、法廷の傍聴席ではモニター越しのやり取りを傍聴することが出来ます。
まとめ
以上が春に改正される法律についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。
相続登記が申請義務化となりました!
・不動産(土地・建物)を相続で取得した人(相続人)は相続したことを知った日 から3年以内に登記をしなければなりません。
相続登記の義務を履行しなかったら?
・正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性 があります。
相続人申告登記が新設されました!
・相続登記の申請義務の履行を簡易な方法でできる新たな登記です。
どのように申請するの?
・登記官に相続人が相続の開始と自らが相続人であることを申出て、当該相続人の戸籍 謄本を提出します。
民法改正で「懲戒権」が削除されました!
・民法821条で子の人格を尊重し、体罰の禁止が明記されました。
嫡出推定制度の見直しがされました!
・女性の再婚禁止期間がなくなり、嫡出推定期間で解釈が変わりました。
口頭弁論がウェブ会議で参加できるようになりました!
・法廷にモニターが設置され、ウェブ会議((映像と音声付の方法)での参加が可能に なり、これまで通り傍聴席で傍聴もできます。
この記事の監修者
代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。
その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。
モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。
<保有資格>
・宅地取引主任者(2004年取得)
・貸金業務取扱主任者(20009年取得)
・司法書士(2009年取得)
・行政書士(2010年取得)
<所属法人>
・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員
・行政書士法人やなぎグループ 代表社員
・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
・桜ことのは日本語学院 代表理事
・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください
当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。
<相談場所>
・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)
・弊所東京事務所(アクセスはこちら)
・オンライン相談
<相談対応>
・平日9:00〜20:00
・土日祝も対応(10:00〜18:00)
・事前の予約で出張対応も可能
私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
お問い合わせ先
相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
<お電話>
フリーダイヤル 0120-021-462
受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00
<メール>
受付時間 24時間受付中