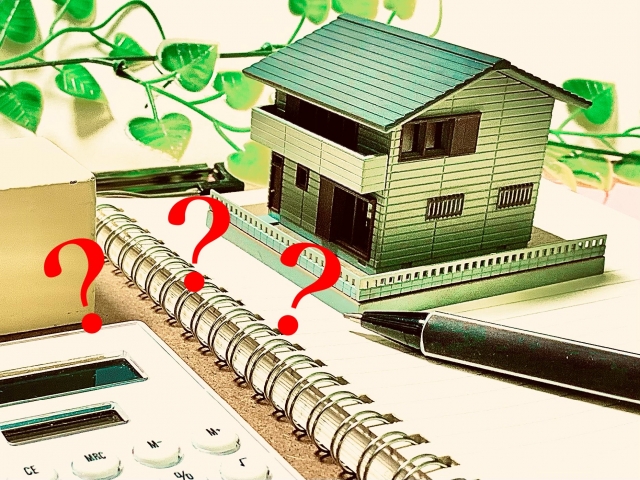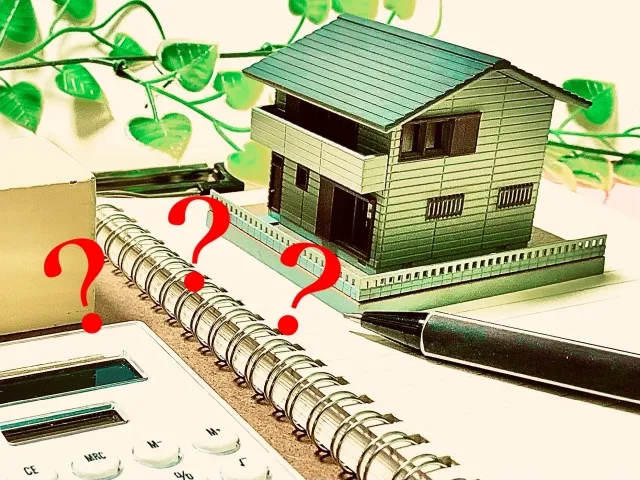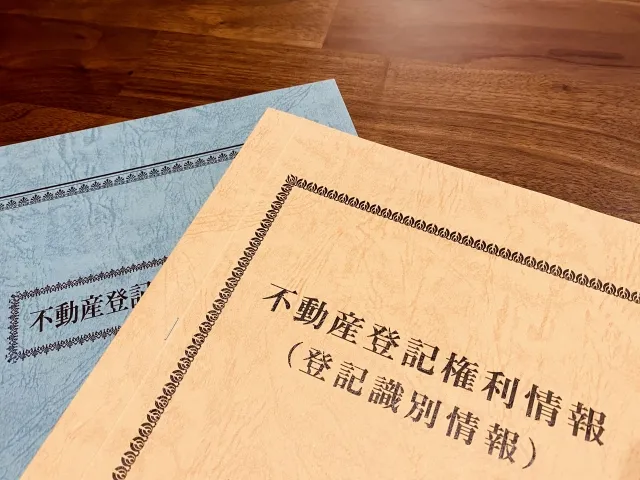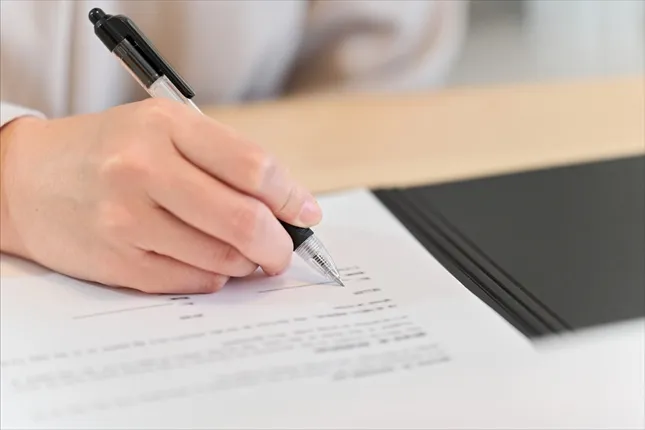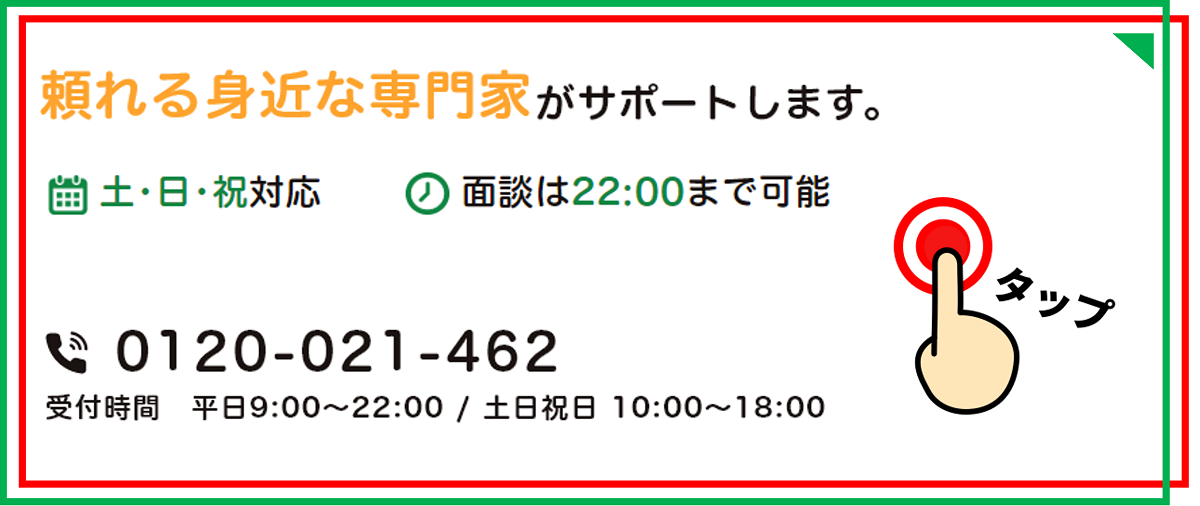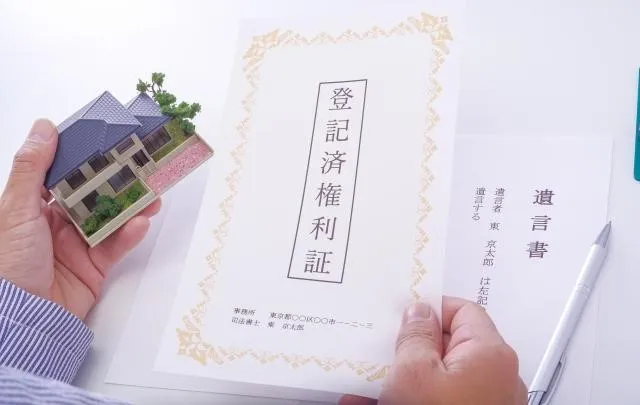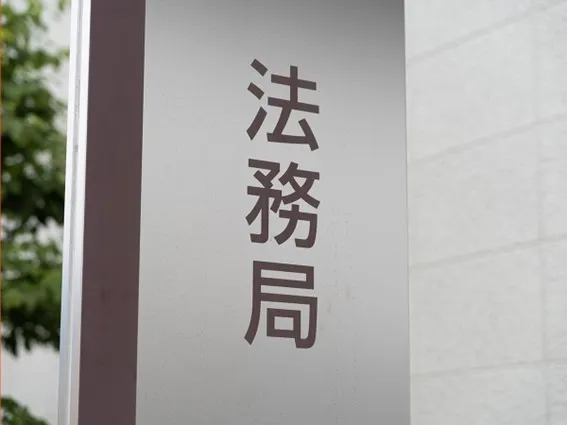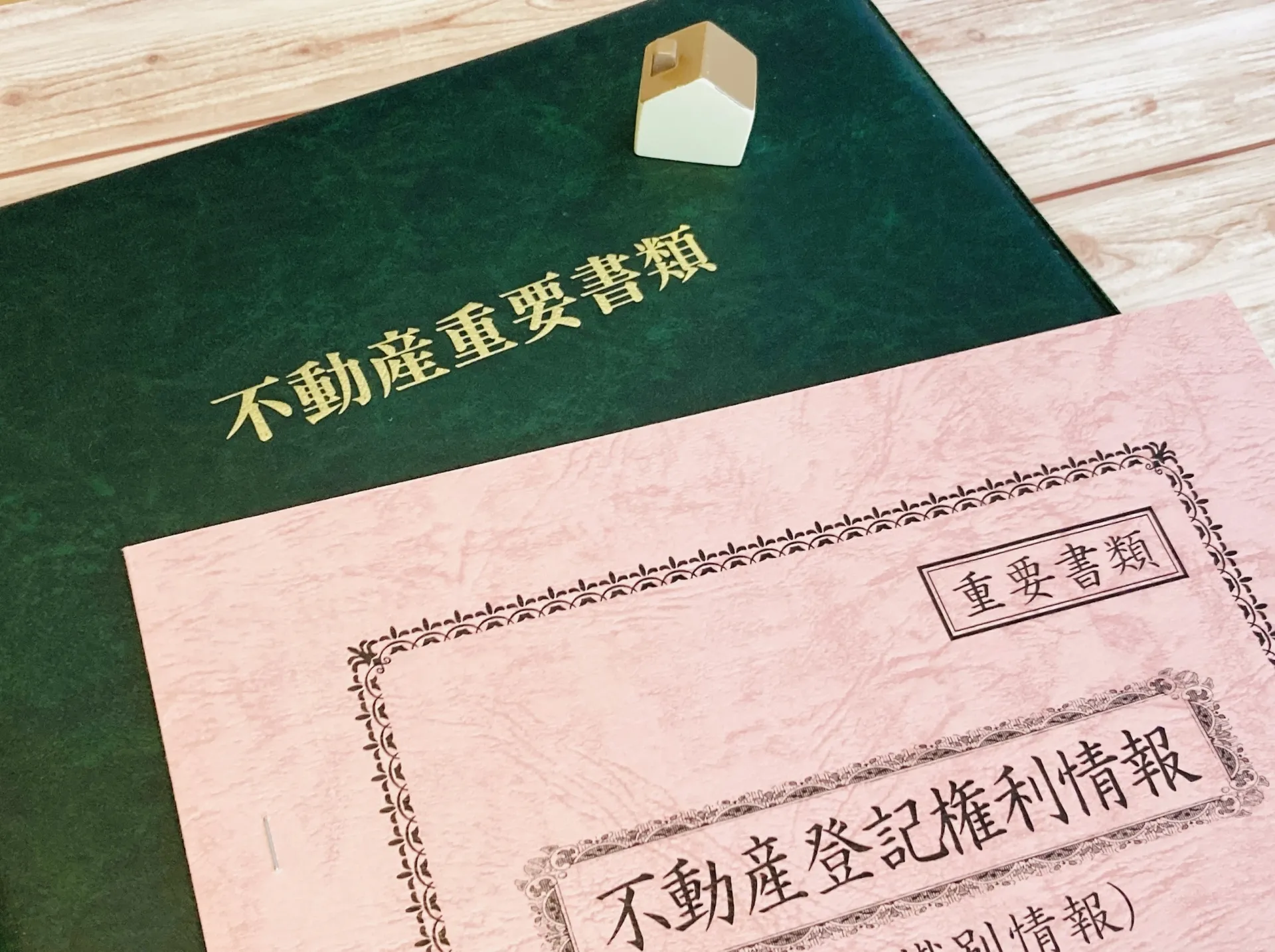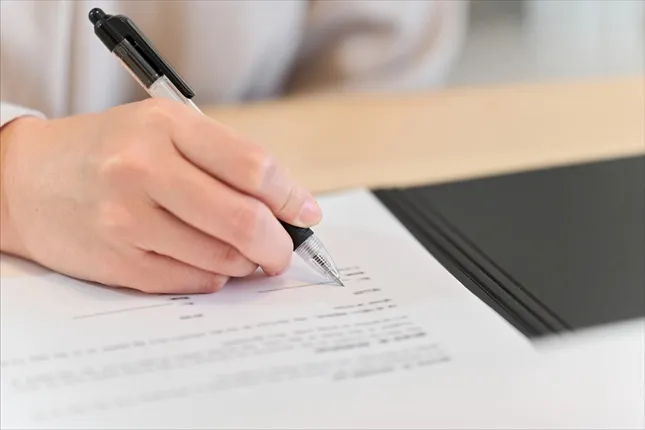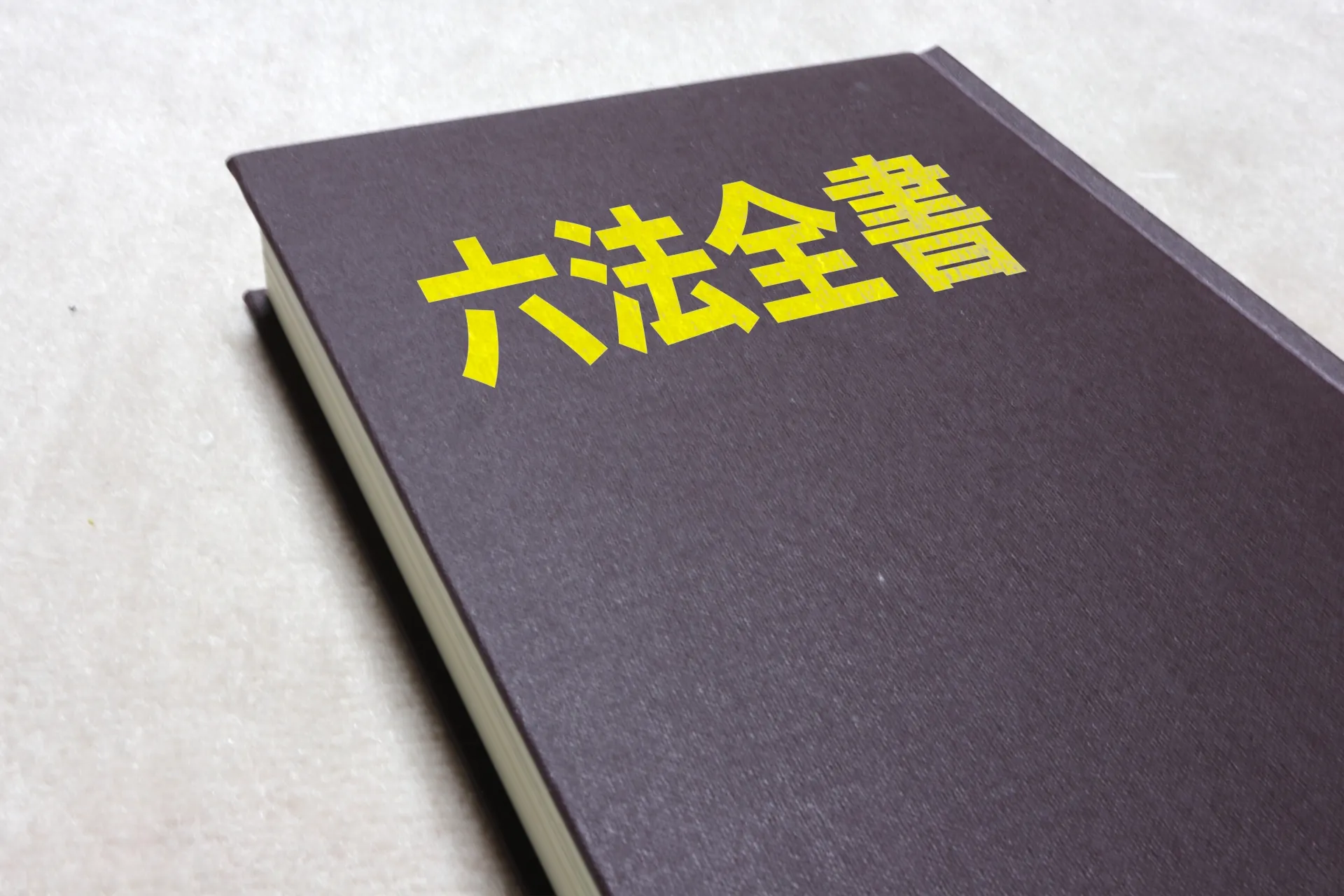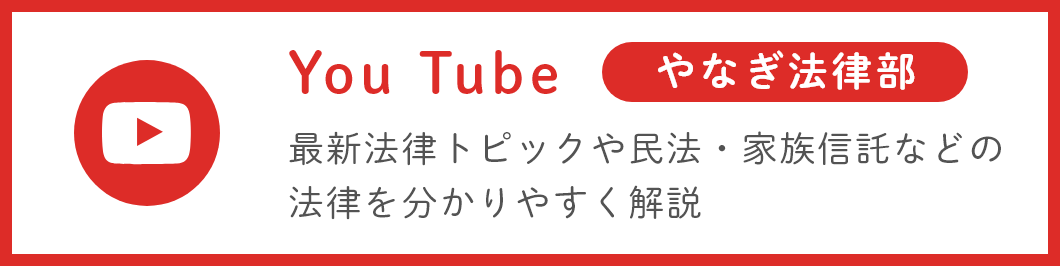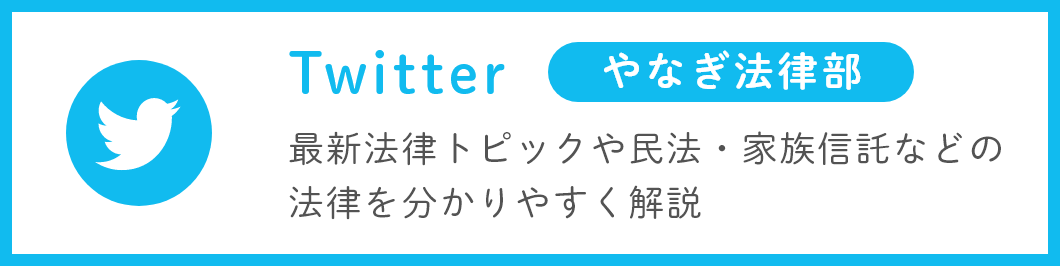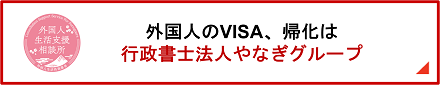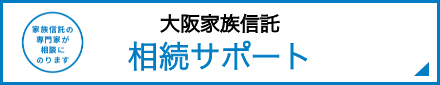令和7年8月23日(土)30日(土)の2日間!夏の個別相談会実施。事前予約開始♪
家族のために無料で相談してみませんか?
・相続登記がまだできていない方
・自分で手続きをしようとしたけど分からなくなってそのままにしている方
・なにからどのように進めて行けばいいか分からない方
・相続した不動産をそのまましている方
・遠方で管理ができない、残地処理で困っている方
普段家族で話すことがない相続や資産の遺し方などをこの機会に話してみませんか?
【予約詳細はこちら】
令和7年8月23日(土)・30日(土)の2日間限定
個別無料相談会を弊所『司法書士法人やなぎ総合法務事務所 あべのベルタ3階』にて開催いたします。
只今、ご予約を受け付けておりますが、各日限定20組のご相談となります。
予約が埋まる前に、お早目のご連絡をお願いします。
2025.07.01 大阪市,あべの,天王寺,相続,相談,無料
【年末年始休業のお知らせ】
誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせて頂きます
ご不便をおかけ致しますが何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます
12月28日(土)~1月5日(日)
新年1月6日(月)から通常営業致します
本年はご愛願いただき、誠にありがとうございました
来年もどうぞよろしくお願い致します
2024.12.27
不動産の売買・贈与の手続きを自分でするときのポイント
今回のお話は、生前対策として不動産の売買・贈与を検討されている方や隣人同士で不動産の売買・贈与を検討されている方に向けた内容となっております。このような方の中には「不動産の売買・贈与の手続きは自分でできるものなのか?」、「不動産の売買・贈与の手続きを自分でするときのポイントは?」等の疑問を持たれる方もおられると思います。今回のブログでは不動産の売買・贈与の手続きのポイントについて説明していきます。不動産の売買・贈与の手続きについて気になる方は本ブログを参考にしていただけると幸いです。
目次
1 不動産の贈与契約書・売買契約書
不動産の売買や贈与は当事者同士の合意で成立しますが、後のトラブルを避けるためには契約書の作成をおすすめします。ここでは、不動産の売買契約書・贈与契約書作成時の注意点を説明していきます。
・ 相場からかけ離れた売買価格のリスク
不動産の知識が不足していると、適正な売買価格の設定が難しいです。市場価格よりかなり安い価格を設定すると、みなし贈与として贈与税が課される可能性があるため、適正価格を確認し、適正価格の範囲で売買することが重要です。・固定資産税など諸費用の精算
不動産の取引には売買代金のほかにも、固定資産税や都市計画税、マンションの場合は管理費や修繕積立金などの諸費用が関わります。これらを精算しないと後でトラブルの原因になります。・物件漏れのリスク
私道やゴミ置き場の共有持分、マンションの集会所や事務所の共有持分など、記載漏れが生じやすいです。これらの細部まで漏れなく記載することが重要です。・担保の見逃しリスク
不動産の登記記録を確認する際、不慣れだと古い担保や買戻特約がついているのを見逃す可能性があります。売買・贈与前にしっかりと登記事項証明書を確認することが必要です。・代金決済と引渡し
売買契約の締結時に代金決済(売買代金の支払い)と物件の引渡しを同日に行うことが一般的ですが、契約内容次第で別の日に設定することも可能です。所有権の移転時期についての定めも確認し、代金支払い完了後に所有権移転登記の申請を行うよう注意しましょう。なお、代金の支払いと不動産の所有権移転登記は、リスクを避けるために、同時に行うようにしましょう。2 登記の申請
相続登記についてはこれを義務化する法律が成立し、2024年4月1日に施行されましたが、贈与・売買登記にはこのような法律はなく法的義務ではありません。そのため、売買・贈与登記を申請しなくても売買・贈与が無効になるわけではありません。売買・贈与登記を申請するか否かは当事者の判断に任されています。しかし、売買・贈与登記をしないことによりトラブルになる可能性があります。ここでは、売買・贈与登記をしないことにより起こるトラブルや登記の手続について説明していきます。
2-1 登記しないと起こりうるトラブル
第三者への売却のリスク: 売買・贈与登記をしていないと、元の所有者が第三者に不動産を売却し、第三者の名義になってしまう可能性があります。
贈与者の死亡による相続問題: 売買・贈与登記をしていないと、売主・贈与者の死亡後に他の相続人が不動産の所有権を主張し、相続財産とされてしまう可能性があります。このように売買・贈与登記を申請しておかないと、後々トラブルにつながる可能性があります。売買・贈与を受けた際には自分の権利を守るためにも早めに売買・贈与登記を申請することをおすすめします。
2-2 登記の申請に必要な書類
登記の申請に必要な書類
不動産の売買や贈与登記を申請する際には、以下の書類が必要です。売主・贈与者に必要な書類
登記済権利証または登記識別情報通知: 所有権を証明するための書類。
印鑑証明書: 発行から3カ月以内のもの。
固定資産評価証明書: 売買・贈与登記をする年度のもの。
登記原因証明情報: 権利の変動の原因を示す書類。不動産売買契約書や贈与契約書がこれにあたる。また、登記の原因となった法律行為が発生したことやその内容を記載した書面を別途作成して提出することも可能。買主・受贈者に必要な書類
住民票の写し: 現住所を証明するための書類※登記済権利証と登記識別情報について
登記済権利証(権利証)とは
登記済権利証、通称「権利証」とは、不動産の所有権を取得する登記が完了した際に法務局から発行される書類です。この書類は所有者しか持っていないものであり、所有権の証明として非常に重要な役割を果たしてきました。
登記識別情報の導入
平成17年の法改正により、登記済権利証に代わって「登記識別情報」が導入されました。登記識別情報は12桁の符号で構成されており、この情報を知っていることが所有者であることの証明となります。これは、従来の紙の書類に代わる電子的な証明方法です。※登記申請前に確認すべきこと
氏名・住所の変更登記の必要性
売買・贈与登記を申請する前に、売主・贈与者の現在の氏名や住所が登記簿上のものと異なる場合は、氏名・住所の変更登記を行う必要があります。これは、正確な登記情報を保つために不可欠です。担保や買戻特約の抹消登記
不動産に設定されている担保や買戻特約がある場合、これらを見逃すと後々のトラブルの原因となります。売買や贈与の前に、必ずこれらの抹消登記を行うことが重要です。3 不動産の売買・贈与の手続費用
・譲渡所得税
不動産売却時に発生する譲渡益に対して所得税や住民税が課税されます。所有期間や用途により税率が変わります。・贈与税
贈与を受けた財産の価額が基礎控除額を超える場合、その超過分に贈与税が課されます。高額な税率となるため、制度を利用して税額を軽減する方法を検討することが重要です。・不動産取得税
不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税です。固定資産税評価額の一定割合で計算されますが、軽減措置もあります。・登録免許税
登記申請の際に納める税金です。4 まとめ
売買・贈与登記を自分で申請するときには、対象不動産の権利関係の確認や売買・贈与契約書の作成など法律的な知識が必要になります。また、登録免許税のほかにも譲渡所得税、贈与税、不動産取得税などの税金が生じますので、どのくらいの税金を納める必要があるかを検討することも大切です。
書類に不備があって贈与登記がやり直しになってしまったとか、売買・贈与したら思っていた以上に税金がかかってしまったということがないように、不動産の売買・贈与を検討する場合は司法書士や税理士などの専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
台風接近に伴い8月31日の個別相談会は延期とさせて頂きます。
現在大型台風接近の為、弊所で開催させて頂きます8月31日の個別相談会は延期とさせて頂きます。 ご予約頂いている方は別日に日程変更の連絡をさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
2024.08.29
株式会社と合同会社はどう違うの?
独立や起業を考える場合、会社を設立するという選択肢があります。会社にも様々な種類があり、「結局、どれにすればいいかわからない」とお悩みの方もおられると思います。今回のブログでは様々種類がある会社の中から「株式会社」と「合同会社」の違いについて説明していきます。株式会社と合同会社の違いについて気になる方は本ブログを参考にしていただけると幸いです。
目次
株式会社・合同会社とは?
「独立」「起業」と聞くと個人事業主の場合もありますが、一般的には会社を設立するイメージを持つ方も多いかと思います。
その中でも「株式会社は聞き覚えがありますが、合同会社は聞いたことがないです。」という方もおられると思います。
以下では「株式会社・合同会社とは何か?」ついて説明していきます。
株式会社とは?
株式会社は、株式を発行してお金を集め、事業活動で利益を得て、その利益を株主に分配することを目的とする組織です。
具体的に言うと、株主は株式会社にお金を出資し、その見返りとして株式を持ちます。株主は、会社の経営を任せるために取締役を選びます。選ばれた取締役は、集めたお金を使って会社を運営し、利益を上げます。その利益は、株主に配当として分配されます。
株式会社の特徴として、所有者である株主と、会社を実際に運営する取締役が別々の人である可能性があります。株主も取締役も同じ1人の方がして、1人で株式会社を設立することも可能です。
合同会社とは?
合同会社は、株式会社とは違い、所有者と経営者が同じであることが特徴です。合同会社にお金を出資した人を「社員」と呼びますが、ここでいう社員は従業員のことではありません。
合同会社では、出資した全ての社員が会社の決定権を持ち、経営に参加します。つまり、会社の所有者である社員全員が、経営の意思決定に関与する仕組みです。
株式会社と合同会社の違い
以下では「株式会社」と「合同会社」の違いについて説明していきます。
株式会社では、会社の所有者は出資者である「株主」です。たとえ経営トップでも、多くの株を持っている人がいれば、その人の意見に配慮する必要があります。これは、株を多く持つほど会社の決定に影響を与える権利が大きくなるからです。この仕組みにより、経営者が勝手に会社を運営するのを防ぎます。
一方、合同会社では、出資者自身が経営を行います。合同会社では、事前に定めたルール(定款)に従って、次のようなことが可能です。
- 出資額に関係なく、貢献度に応じて利益を配分できる。
- 出資比率に関係なく、議決権を与えることができる。
- 経営を行う社員と、経営を行わない社員を決められる。
- 定款の変更に全社員の同意を必要としないようにできる。
このように、株式会社と違って、合同会社では出資者に相談する必要がなく、自由な経営が可能です。
意思決定に必要なこと
株式会社の場合、 重要な決定をするためには「株主総会」を開いて決めなければならず、場所の確保やスケジュール調整などに時間がかかります。
合同会社の場合、 全社員が同意すれば、すぐに決定できます。社員が少ない場合、調整が簡単なので、意思決定が速く行えます。
合同会社の方が、事業の方針を柔軟に変更したり、すぐに撤退を判断したりすることができます。有名企業においても、例えば、DMM.comは意思決定を迅速化するために合同会社になりました。他にも、AppleやGoogle、Amazonといった外資系企業も合同会社を選んでいます。
設立時の手続きと費用
株式会社の場合、 定款を作成し、さらに公証役場で「定款の認証」を受ける必要があります。設立費用は約20.3万円(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)かかります。
合同会社の場合、 定款の認証が不要で、設立費用は約6万円(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)で済みます。
決算公告の義務
株式会社の場合、 毎年、決算状況を公開する「決算公告」を行う義務があります。公告方法としては、官報に掲載(約7万円)、日刊新聞に掲載(数十万円~)、自社Webサイトに掲載(費用は0円)などがあります。
合同会社の場合、 決算公告を行う義務がありません。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
結局「株式会社か合同会社かどちらがいいの?」という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを解説しますので、株式会社か合同会社かを選択する際の参考にしていただければと思います。
株式会社のメリット・デメリット
メリット
- 知名度と信用:
- 株式会社は合同会社よりも知名度が高く、社会的信用も高いです。多くの人に知られているため、会社の認知度を上げたい場合に有利です。
- 安定した運営:
- 株式会社では、複数の出資者(株主)がいる場合でも、多くの株を持つ株主の意見が強く反映されるため、安定した意思決定が可能です。仲間で資金を出し合って会社を設立する場合には、株式会社が適しています。
デメリット
- 決算の公告義務:
- 株式会社は毎年決算の内容を公開する義務があります。これには費用がかかるため、デメリットといえます。
- 役員の任期と登記費用:
- 株式会社の役員(取締役)の任期は最長で10年(非公開会社の場合)で、その都度役員変更の登記を行う必要があります。これに伴う費用もかかります。
合同会社に比べると、株式会社は広く知られていて信用が高い一方で、定期的な手続きや費用がかかる点がデメリットです。
合同会社のメリット・デメリット
メリット
- 設立費用が安い:
- 定款の認証が不要で、登録免許税が最低額の場合6万円と、株式会社よりも安く済みます。
- 設立費用が低く抑えられます。
- 役員の任期がない:
- 合同会社の業務執行社員は任期がないため、役員変更の登記が必要なく、その分費用も抑えられます。
- 決算公告の義務がない:
- 合同会社は毎年の決算公告が不要です。そのため、公告の費用がかからず、費用が抑えられます。
デメリット
- 知名度が低い:
- 合同会社は株式会社に比べて認知度が低いです。近年、アマゾンやアップルの日本法人が合同会社であることで徐々に知名度が上がっていますが、まだ株式会社には及びません。
- 経営の対立の可能性:
- 合同会社では出資比率に関係なく一人一票の議決権を持つことが多いため、社員同士で意見が対立すると経営や業務が難しくなることがあります。
合同会社は設立費用や維持費用が安く、柔軟な運営が可能ですが、知名度の低さや社員同士の対立のリスクがあります。
まとめ
以上が「株式会社と合同会社はどう違うの? 」についてのお話でした。ここまでのお話を以下にまとめています。
株式会社・合同会社とは?
- 株式会社: 株式を発行して資金を集め、事業で利益を得て株主に分配する組織。所有者は株主で、経営は取締役が行う。
- 合同会社: 所有者と経営者が同一である組織。出資者を「社員」と呼び、全員が経営に参加する。
株式会社と合同会社の違い
- 所有者と経営者の関係:
- 株式会社: 所有者は株主で、経営者は取締役。多くの株を持つ株主が大きな影響力を持つ。
- 合同会社: 所有者がそのまま経営者となる。出資額に関係なく、貢献度に応じて利益を配分し、議決権も持つ。
- 意思決定の方法:
- 株式会社: 株主総会を開いて決議を行うため、時間がかかる。
- 合同会社: 全社員の同意で迅速に決定できる。
- 設立時の手続きと費用:
- 株式会社: 定款の認証が必要で、設立費用は約20.3万円。
(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)。
- 合同会社: 定款の認証が不要で、設立費用は約6万円。
(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)
- 決算公告の義務:
- 株式会社: 毎年決算を公告する義務がある(費用がかかる)。
- 合同会社: 決算公告の義務がない。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
株式会社
- メリット:
- 知名度と信用が高い。
- 複数の株主がいても安定した意思決定が可能。
- デメリット:
- 決算公告の義務があり、費用がかかる。
- 役員の任期があり、任期ごとに登記費用がかかる。
合同会社
- メリット:
- 設立費用が安い。
- 役員の任期がなく、登記費用が抑えられる。
- 決算公告の義務がない。
- デメリット:
- 知名度が低い。
- 一人一票の議決権のため、社員同士の対立が経営に影響する可能性がある。
株式会社と合同会社は、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。会社設立の目的や状況に応じて、どちらの形態が適しているかを選ぶことが重要です。


相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
抵当権抹消を放置するとどうなる?
不動産を購入する際、ローンを組まれる方が多いと思います。ローンを無事返済した後も法務局の手続が必要なのはご存じでしょうか?「法務局の手続はしないといけないのか?」、「法務局の手続きを放置するととどうなる?」等の疑問をお持ちの方もおられると思います。今回は抵当権抹消を放置するととどうなる、抵当権の抹消方法を説明していきます。抵当権抹消についてお知りになりたい方は参考にしていただければ幸いです。
目次
抵当権とは?
金融機関は融資をする際に、お金を借りる人から担保を取ります。担保には、人的担保と物的担保の2種類に分かれます。
このうち、お金を貸すときに家や土地などの不動産を担保する権利のことを「抵当権」と言います。
1-1. 人的担保と物的担保
人的担保とは、対象の債務に対して、債務者以外の第三者が責任を負う担保のことです。代表的な人的担保は保証契約です。単なる保証契約では、保証人が債権者から支払いを要求された際に、先に債務者に返済の請求をするように主張できる「催告の抗弁権」、保証人が債権者に対して、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証の責務を拒否出来る権利の「検索の抗弁権」が保証人に認められているため、実務上はそれらがない連帯保証契約が用いられることが多いです。
それに対し、物的担保とは、物を担保として取るということです。 代表的なものとして、抵当権や質権があげられます。返済が滞った場合は、担保として提供された物を競売にかけ、その競売代金などから、優先的に債権を回収することができます。
抵当権が設定されても、所有者は担保にした不動産を使用することができます。ただし、返済が滞った場合は、金融機関などの抵当権者は担保不動産を競売にかけて売却し、その代金から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができます。
1-2. なぜ抵当権は登記されるのか?
抵当権を含む不動産の権利は、登記をしなければ第三者に主張できないと条文によって定められています。そのため、金融機関などは債券回収の際に権利を主張するために、抵当権を設定した時は登記をします。
抵当権の登記は、債権額、債務者の氏名または名称および住所、利息などが登記事項となります。返済が滞った場合には抵当権が実行されますが、多くの場合は、債務者の弁済により消滅します。しかし、債務を弁済しても、登記された抵当権は自動的に抹消されることはありません。抵当権抹消登記を申請し、登記が完了して初めて、土地や建物に設定されていた抵当権が登記簿から消滅します。
抵当権抹消を放置するとどうなる?
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続登記を放置した場合、過料の対象になりますが、以下では抵当権抹消を放置するとどうなるかについて説明していきます。
不動産の売却が困難になる
登記簿上に抵当権が残ったままでも、すぐに実害があるわけではありません。
しかし、長い目で見れば、抵当権抹消登記をしないことによるデメリットは存在します。
一番のデメリットは、抵当権抹消登記をしないと不動産の売却が困難になる点です。
ほぼすべての売買契約書で、売主は抵当権などの登記のないきれいな状態で不動産を引き渡さなければならない旨の条項が記載されています。
実際に抵当権の登記がある不動産の売買では、既に完済していれば売買による名義変更と、事前または同時に、売却代金をもって完済の手続きをするということであれば名義変更と同時に、抵当権抹消登記の手続きをおこないます。
第三者からすれば登記簿を見て、抵当権が抹消されているかの判断するしかないので、実際にはローンを完済していたとしても、登記簿上に抵当権の登記が残ったままだと完済したかどうかの判断ができません。
不動産を売買する際、買う側としては、抵当権の登記が残ったままの不動産を買おうとは思いません。法律上は、抵当権の登記が残ったままでも売却をすること自体は問題ありませんが、抵当権の登記が残ったままの不動産に基本的に買い手がつかないため、そういった意味で、実質的に抵当権抹消登記をしないと売却はできません。
抵当権抹消登記をしないでいると、いざ処分しようとなったときに抵当権の登記が障害となってしまう場合があります。
抵当権抹消に必要な書類や費用が増加する可能性
その他のリスクとしては、いざ手続きをやろうとしたときに余計な手間や費用がかかってしまう恐れがあるということです。
住宅ローンの完済後に金融機関から交付される書類には、金融機関名や所在地、その代表者の氏名が記載されているものがあります。
書類を受け取った後に放置すると、代表者が変わったり、所在地を移転したりと、書類に記載されている内容に変更が生じる可能性があります。
中には、合併などによりそもそも金融機関が消滅してしまったということもあります。
手続きをしない間に、別の書類が必要になったり、場合によっては金融機関に書類の再発行を依頼するこ手間がかかります。
もし、抵当権抹消の手続きを自身でやろうにも、非常に困難になり、余計な費用もかかってしまう可能性もあります。
また、抵当権抹消登記の手続きをしないまま名義人が亡くなると、その相続人が抵当権抹消登記の手続きをすることになり、相続人に手続きの手間や、金銭面において負担をかけることになってしまいます。その為、抵当権抹消登記は金融機関から書類を受け取ったら、すぐに手続きを済ませることをおすすめします。
抵当権の抹消方法
次に、抵当権抹消登記の申請方法を説明します。
3-1. 登記手続きの流れ
登記手続きの流れは以下の通りです。
➀資料、書類の収集
抵当権者から必要書類を受け取ります。必要書類としては、委任状、登記原因証明情報(解除証書など)、抵当権についての登記識別情報または登記済証が必要となります。
次に法務局で、抵当権が設定されている不動産の登記事項証明書を共同担保目録付きですべて取得します。共同担保目録には担保に入っている不動産が記載されているため、証明書の取得漏れがないかを確認します。クレジットカードを持っている場合は、インターネットの『登記情報提供サービス』で登記情報を見ることができ、法務局で証明書を取得する手間を省くことができます。
➁登記申請書の作成
書式は法務局のホームページからダウンロードできます。
主な記載内容は、登記の目的(抵当権抹消)、原因内容(弁済など)やその年月日、権利者・義務者名などです。
③ 法務局への申請
申請方法は、管轄の法務局の窓口に申請書を提出、または郵送する方法があります。電子署名ができ、登記原因証明情報をPDFファイルにすることができる人は、オンライン申請(添付書類は窓口提出か郵送)も可能です。不動産の所在地によって申請先の管轄法務局は変わるため、法務局のホームページで確認が必要です。
3-2. 抵当権抹消登記の費用は?
抹消登記には登録免許税が課税されます。
登録免許税は、不動産の個数×1000円です。登録免許税としては、物件数が多くなければ高額にはなりませんが、書類を集めて申請することは、手間と時間を要するため、司法書士のような専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
以上が「抵当権抹消を放置するとどうなる? 」についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。
抵当権とは?
・お金を貸すときに家や土地などの不動産を担保する権利のことを「抵当権」と言います。
・担保には、人的担保と物的担保の2種類に分かれます。人的担保とは、対象の債務に対して、債務者以外の第三者が責任を負う担保のことで、物的担保とは、物を担保として取るということです。 代表的なものとして、抵当権があげられます。返済が滞った場合は、担保として提供された物を競売にかけ、その競売代金などから、優先的に債権を回収することができます。
・抵当権が設定されても、所有者は担保にした不動産を使用することができます。ただし、返済が滞った場合は、金融機関などの抵当権者は担保不動産を競売にかけて売却し、その代金から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができます。
抵当権抹消を放置するとどうなる?
・2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続登記を放置した場合、過料の対象になりますが、登記簿上に抵当権が残ったままでも、すぐに実害があるわけではありません。
・長い目で見れば、抵当権抹消登記をしないことによるデメリットも存在し、一番は、抵当権抹消登記をしないと不動産の売却が困難になる点です。
ほぼすべての売買契約書で、売主は抵当権などの登記のないきれいな状態で不動産を引き渡さなければならない旨の条項が記載されているためです。
・実際に抵当権の登記がある不動産の売買では、既に完済していれば売買による名義変更と、事前または同時に、売却代金をもって完済の手続きをするということであれば名義変更と同時に、抵当権抹消登記の手続きをおこないます。
・住宅ローンの完済後に金融機関から交付される書類には、金融機関名や所在地、その代表者の氏名が記載されているものがあり、書類を受け取った後に放置すると、代表者が変わったり、所在地を移転したりと、そもそも合併などにより金融機関が消滅している場合もあり、いざ手続きをやろうとしたときに余計な手間や費用がかかってしまう恐れがあります。
抵当権の抹消方法
・抵当権者から委任状、登記原因証明情報(解除証書など)、登記識別情報または登記済証の必要書類を収集します。
・法務局で、抵当権が設定されている不動産の登記事項証明書を共同担保目録付きですべて取得し、証明書の取得漏れがないかを確認します。クレジットカードを持っている場合は、インターネットの『登記情報提供サービス』で登記情報を見ることができます。
・書式は法務局のホームページからダウンロードでき、主な記載内容は、登記の目的(抵当権抹消)、原因内容(弁済など)やその年月日、権利者・義務者名などです。
・申請方法は、管轄の法務局の窓口に申請書を提出、または郵送する方法があり、不動産の所在地によって申請先の管轄法務局は変わるため、法務局のホームページで確認が必要です。
・抹消登記には登録免許税が課税され、抵当権抹消登録の登録免許税は、不動産の個数×1000円です。


相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
役員変更登記を放置すれば解散!?
令和6年4月1日に相続登記の義務化が始まり気になっている方もおられるのではないでしょうか。しかし、登記が義務になっているのは不動産だけではありません。会社の登記も義務になっているものがあります。その中でも今回は株式会社の役員変更を忘れるとどうなるかについて説明していきます。株式会社の役員変更をお忘れの方やこれから株式会社の役員変更を検討されている方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
1 役員変更の登記をしないと罰則!?
1-1 役員変更の登記をするべき時期
1-2 役員変更の登記をしないと罰則!?
2 役員変更をしないと会社が解散させられる!?
2-1 みなし解散とは?
2-2 みなし解散がされるまでの手続きの流れ
3 役員変更とみなし解散がされた場合の登記
3-1 役員変更の登記
3-2 継続の登記
4 まとめ
役員変更をしないと罰則
はじめに株式会社の役員変更の登記はいつ行うべきなのか、また行わない場合はどのような罰則があるのかについて説明します。株式会社の役員変更の登記をする時期について知りたい方は参考にしていただければ幸いです。
役員変更の登記をするべき時期
取締役の任期は別段の定めが無い限り、選任後2年以内、監査役の任期は選任後4年以内です。
定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です(詳細につきましてはhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.htmlをご参照ください。)。
また、公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより延ばすことができ、選任後最大10年以内となります。
公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部又は一部を、株式の譲渡について株式会社の承認が必要という旨の定款の定めがない株式会社のことをいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係なく、株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません。
役員変更の登記をしないと罰則!?
登記すべき期間が過ぎた後に登記申請を行ったとしても、期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に科せられる可能性があります。
役員変更をしないと会社が解散させられる!?
前述のとおり役員変更を忘れると、過料に科せられます。以下では株式会社の登記をさらに放置するとどうなるかについて説明していきます。
みなし解散とは?
株式会社の場合、役員の変更の登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過したとき、休眠整理作業の対象となり、その後も登記もしくは事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになります。
実際は動いている会社でも登記申請を怠っていた場合、解散の登記がされてしまうことになります。そうなると会社の運営・経営に支障をきたすこととなり、また、継続の登記をしなければならなくなるため、費用もかかります。ご自身の会社の登記申請手続きが適切になされているかどうか、一度ご確認をおすすめします。
みなし解散がされるまでの手続きの流れ
全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
毎年10月頃、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。その後、2か月以内に役員変更等の必要な登記、もしくは「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、同様にみなし解散の登記がなされるため、注意が必要です。
届出をする際は、登記所からの通知書の下段にある「届出書」に記載し、登記所に送付もしくは持参をします。また、代理人による届出をするときは、委任状の添付が必要です。通知書を利用できない場合には、書面に以下の事項を記載し、提出します。
【届出書に記載すべき内容】
(1) 休眠会社の場合 商号、本店並びに代表者の氏名及び住所
休眠一般法人の場合 名称、主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人による届出 その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 届出の年月日
(5) 登記所の表示
不備があると、適正な届出として認められないことがあるため、正確に記載する必要があります。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わななければ、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となるため、注意が必要です。
なお、この届出又は必要な登記申請がされた場合であっても、それ以前の登記を怠ったことについては、裁判所から過料に処せられる可能性があるため、変更があった場合は必要な登記申請を怠らないようにする必要があります。
役員変更とみなし解散がされた場合の登記
過料やみなし解散にならないためには役員変更の登記が必要ですが方法がわからない方もおられると思います。また、みなし解散になった場合に株式会社を継続する方法がわからないという方もおられると思います。以下では役員変更とみなし解散がされた場合の登記について説明していきます。
役員変更の登記
役員変更における株式会社変更登記申請書に必要な記載事項は以下のものとなります。
・会社法人等番号(分かる場合、記載する)
・商号(フリガナ)
フリガナは会社の種類(株式会社)を除いてカタカナで左に詰めて記載する。
・本店(住所)
・登記の事由
取締役及び代表取締役の変更など
添付書類としては以下のものとなります(非公開会社・取締役会非設置会社・取締役1人・再度就任の場合)。
・株主総会議事録
・株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・就任承諾書(株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載及び被選任者の住所の記載が議事録にある場合は不要)
・定款(株主総会議事録に取締役の任期が満了する旨の記載がある場合は不要。)
・委任状(代理人に申請を委任した場合のみ)
申請書の最後には、本店(住所)、商号、代表取締役の住所、代理人の住所を記載し、登記所に提出した印鑑を押印します。
また、代理人が申請する場合にのみ、代理人の印鑑を押印し、代表取締役の押印は必要ありません。
登記申請には、登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があり、資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円となります。
継続の登記
みなし解散の登記後の3年以内に限り、 株式会社は、株主総会の特別決議によって、会社・法人を継続することができます。
会社・法人を継続したときは、その決議から2週間以内に、継続の登記の申請をする必要があります。
株式会社継続登記申請書に必要な記載事項は以下のものとなります。
・会社法人等番号(分かる場合、記載する)
・商号(フリガナ)
フリガナは会社の種類(株式会社)を除いてカタカナで左に詰めて記載する。
・本店(住所)
・登記の事由
会社継続 取締役、代表取締役就任など
添付書類は以下のものとなります(非公開会社・取締役会非設置会社・取締役1人の場合)。
・株主総会議事録
・株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・就任承諾書
・印鑑証明書
・委任状
申請書の最後には、本店(住所)、商号、代表取締役の住所、代理人の住所を記載し、登記所に提出した印鑑を押印します。
また、代理人が申請する場合にのみ、代理人の印鑑を押印し、代表取締役の押印は必要ありません。
会社継続の登記申請には、3万円の登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があります。
まとめ
以上が役員変更登記を放置すれば解散!?についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。
役員変更
・取締役の任期は、別段の定めの無い限り、選任後2年以内に、監査役の任期は選任後4年以内です。
・定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です。
・公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に伸長することが可能です。
・役員変更については、選任から2週間以内に登記申請しなければなりません。
・登記すべき期間が過ぎた後に登記申請を行った場合、期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
役員変更をしないと会社が解散させられる
・株式会社の場合、役員の変更の登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過したとき、休眠整理作業の対象となり、その後も登記もしくは事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされます。
・実際には活動している会社であっても、登記申請を怠っていると休眠整理作業の対象となり解散したものとみなされます。
・毎年10月頃、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。
・2か月以内に役員変更等の必要な登記、もしくは「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、みなし解散の登記がされることになります。
・届出をする際は、登記所からの通知書の下段にある「届出書」に記載し、登記所に送付もしくは持参をします。
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わななければ、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となるため、注意が必要です。
役員変更とみなし解散がされた場合の登記
・過料やみなし解散にならないためには役員変更の登記が必要です。
・みなし解散の登記後の3年以内に限り、 株式会社は、株主総会の特別決議によって、会社・法人を継続することができます。
・登記申請書に漏れなく正しく記載し、必要な書類を添付しなければならない。
・役員変更登記申請には、登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があり、資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円となります。会社継続の登記申請には、3万円の登録免許税を納める必要があります。
この記事の監修者
代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。
その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。
モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。
<保有資格>
・宅地取引主任者(2004年取得)
・貸金業務取扱主任者(20009年取得)
・司法書士(2009年取得)
・行政書士(2010年取得)
<所属法人>
・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員
・行政書士法人やなぎグループ 代表社員
・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
・桜ことのは日本語学院 代表理事
・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください
当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。
<相談場所>
・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)
・弊所東京事務所(アクセスはこちら)
・オンライン相談
<相談対応>
・平日9:00〜20:00
・土日祝も対応(10:00〜18:00)
・事前の予約で出張対応も可能
私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
お問い合わせ先
相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
<お電話>
フリーダイヤル 0120-021-462
受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00
<メール>
受付時間 24時間受付中
家が売れない!?不動産売買で必要な権利証。無くした場合はどうなるの?
不動産の売買で権利証が必要というお話を聞かれた方も多いと思います。しかし、お持ちの不動産の権利証を失くしてしまったという方もおられると思います。本ブログでは不動産の権利証を失くしてしまった場合の手続について簡単に説明していきます。不動産の権利証を失くしてしまったという方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
1 不動産の権利証とは?
1-1 不動産の権利証とは?
1-2 登記識別情報とは?
2 権利証または登記識別情報を失くしても売買はできるの?
2-1 事前通知
2-2 本人確認情報
3 権利証または登記識別情報を失くして不安な場合の手続
3-1 不正登記防止申出の制度
3-2 登記識別情報の失効の申出の制度
3-3 登記識別情報の不通知
4 まとめ
不動産の権利証とは?
はじめに不動産の権利証とは何かについて説明します。不動産の権利証について知りたい方は参考にしていただければ幸いです。
不動産の権利証とは?
権利証(登記済証)とは、登記が完了した際に登記所から登記名義人に交付する書面です。その後、新しい登記名義人が登記を申請する場合に、本人を確認するために登記所に提出をする、登記手続固有の本人確認手段です。権利証はどの様な理由があっても、再発行はできません。
しかし、この権利証(登記済証)は、書面のままではオンライン申請時において、登記所に提供することが出来ないため、オンライン申請には適していません。そこで、権利証に代わる本人確認情報の手段として、オンライン申請においても利用可能な登記識別情報の制度が導入されました。
権利証には登記が完了したことを証明する機能もありましたが、この機能の代わりとなるものとして、登記完了証が交付されます。
登記識別情報とは?
登記識別情報とは、登記が完了した際に登記所から登記名義人に通知される、12桁の英数字の組合せからなる識別情報です。この登記識別情報は、例えば登記記録上の登記名義人が売主として所有権の移転の登記を申請する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提出します。登記識別情報も権利証同様、再発行はできません。
権利証または登記識別情報を失くしても売買はできるの?
以下では権利証または登記識別情報を失くした場合の売買登記の手続について説明をしていきます。
事前通知
登記識別情報は、不動産に関する所有権の移転の登記などに使用しますが、登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは、 他の方法による申請ができることがあります。具体的には、登記識別情報による本人確認の代わりに、登記所から登記名義人 宛てに送られる、「事前通知」により本人であることの確認をしてもらうことができます。この「事前通知」とは、登記識別情報を提供すべき登記名義人の住所地に、本人限定受取郵便で送られてきます。
通知内容は、登記の申請があった旨、その申請の内容に間違いがない時はその旨を2週間以内に申出をすべきことが通知されています。
この通知に対して、2週間以内に申請に間違いがない旨の申出をすることで、本人からの申請であるということを確認するというものです。
一見便利そうに見えるこの事前通知制度ですが、不動産売買の際には利用されることはありません。なぜなら、事前通知を受ける売主側が事前通知に対する回答を行わない場合、登記申請が却下されてしまうからです。登記申請時に売却代金の授受を行う不動産売買決済時において、確実に売買登記がされる保証のない事前通知制度は事故のもとになってしまうのです。
2-本人確認情報
登記識別情報や権利証を添付できない場合、事前通知を省略して登記申請を行う方法として、司法書士・土地家屋調査士・弁護士の資格者代理人等による本人確認の制度があります。
この制度は、代理人である資格者が申請人と面談を行い、登記名義人本人であることを確認します。この資格者が「本人であることに間違いがない」と確認ができると、事前通知の手続きをすることなく、登記手続きができます。
本人確認のために使用した資料や面談日時、本人確認を行った場所などを明らかにし、本人確認情報として、法務局に提出します。それらが認められれば、登記が実行されます。認められなければ、事前通知の方法で申請を行わなければなりません。
その他にも、公証人から必要な認証をもらい、登記官がその内容を認めれば、事前通知を省略することができます。
権利証または登記識別情報を失くして不安な場合の手続
権利証または登記識別情報を盗難されるまたは失くした場合、悪用される恐れがないかと不安になると思います。以下では権利証または登記識別情報の悪用防止についての手続に説明します。
不正登記防止申出の制度
登記識別情報を取得した者が、登記名義人になりすまして不正な登記を行う可能性が全くないとは言い切れませんし、不正な登記がされた場合には、登記名義人が思わぬ損害を被るおそれもあります。このような場合、登記名義人の権利を防衛するために、不正登記防止申出の制度があります。
この制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度であり、権利の移動を禁止する趣旨の制度ではありません。
紛失した権利証を不正な登記(犯罪)に利用される差し迫った危険があるというような具体的な不安がある場合には、3か月ごとに不正登記防止申出の手続をしなければなりません。
不正登記防止申出の手続は、申出人本人の出頭が原則ですが、やむを得ず、本人が登記所に出頭できない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭して行うこともできますので、申出先の登記所に問い合わせてみると良いでしょう。
登記識別情報の失効の申出の制度
登記識別情報の失効の申出のとは、登記名義人の請求によって、一度、有効に取得した登記識別情報を失効させる制度です。この制度は、登記識別情報を紛失した場合や、盗まれてしまった場合など、登記識別情報を使用した不正登記の防止に利用できます。この請求には登記識別情報の提出は必要はありません。しかし、この請求が登記名義人による請求であることを確認する必要があります。
オンラインによる請求であれば電子署名と電子証明書、書面による請求であれば印鑑証明書付きの印鑑で確認されることになります。
登記識別情報の不通知
登記識別情報は情報そのものであるため、他人に知られるだけで悪用される可能性があります。権利証のように物理的に処分することができません。
そこで、登記識別情報を適切に管理できない・したくないという登記名義人は、事前に登記識別情報の通知を拒否することができ、通知されないようにすることができます。
通知を拒否した者がその後、権利に関する登記を行うには、事前通知制度や資格者代理人などによる本人確認制度を利用することになります。
まとめ
以上が不動産売買で必要な権利証。無くした場合はどうなるの?についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。
不動産の権利証とは?
・登記が完了した際に登記所から登記名義人に交付する書面です。
登記識別情報とは?
・登記識別情報とは、登記が完了した際に登記所から登記名義人に通知される、12桁の英数字の組合せからなる識別情報です。
事前通知とは?
・登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは、 登記識別情報による本人確認の代わりに、登記所から登記名義人 宛てに送られる、「事前通知」により本人であることの 確認をしてもらうことができます。この「事前通知」とは、登記識別情報を提供すべき 登記名義人の住所地に、本人限定受取郵便で送られてきます。
ただし、不動産の売買などでは利用されることはありません。
本人確認情報の方法
・登記識別情報や権利証を添付できない場合、事前通知を省略して登記申請を行う方法として、司法書士・土地家屋調査士・弁護士の資格者代理人等による本人確認の制度があります。
権利証または登記識別情報を失くして不安な場合の手続
・不正登記防止申出の制度があります。
登記識別情報の失効の申出の制度
・登記名義人の請求によって、一度、有効に取得した登記識別情報を失効させる制度です。
登記識別情報の不通知
・登記識別情報を適切に管理できない・したくないという登記名義人は、事前に登記識別情報の通知を拒否することができ、通知されないようにすることができます。
この記事の監修者
代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。
その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。
モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。
<保有資格>
・宅地取引主任者(2004年取得)
・貸金業務取扱主任者(20009年取得)
・司法書士(2009年取得)
・行政書士(2010年取得)
<所属法人>
・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員
・行政書士法人やなぎグループ 代表社員
・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
・桜ことのは日本語学院 代表理事
・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください
当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。
<相談場所>
・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)
・弊所東京事務所(アクセスはこちら)
・オンライン相談
<相談対応>
・平日9:00〜20:00
・土日祝も対応(10:00〜18:00)
・事前の予約で出張対応も可能
私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
お問い合わせ先
相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
<お電話>
フリーダイヤル 0120-021-462
受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00
<メール>
受付時間 24時間受付中
春の法改正特集!4月から改正される法律はこれだ!詳しく解説します
この春、相続登記の申請義務化の制度や民法等多くの法律が改正されました。本ブログではこの春に改正される法律についてどのように改正されるかを簡単に説明していきます。どのように法律が改正されか気になる方等は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
1 相続登記の申請義務化について
1-1 相続登記の申請義務化
1-2 相続人申告登記
2 民法の改正について
2-1 懲戒権の見直し
2-2 嫡出推定制度の見直し
3 民事訴訟法の改正について
3-1 口頭弁論をウェブ会議で参加
4 まとめ
相続登記の申請義務化について
相続登記の申請義務化の制度が令和6年4月1日から始まりました。相続登記がまだお済でない方は参考にしていただければ幸いです。
相続登記の申請義務化
・制度全般について
相続人は、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
不動産(土地・建物)を相続で取得した人(相続人)は相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。また、正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続人間における遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産(正しい登記がされていないもの)においても対象となり、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記が必要となります。
詳細につきましては弊所のブログ(https://yanagi-law.jp/blog/5047)をご覧になって頂けると幸いです。
相続人申告登記
相続人申告登記制度は、相続登記の申請義務を簡易な方法で行えるよう新たな登記として令和6年4月1日にスタートしました。詳細につきましては弊所のブログ(https://yanagi-law.jp/blog/5047)をご覧になって頂けると幸いです。
民法の改正について
令和6年4月1日に民法の一部が改正されます。以下では改正される規定のうち懲戒権と嫡出推定制度について説明をしていきます。
懲戒権の見直し
改正前民法822条「懲戒権」の規定が削除されました。懲戒権は、児童虐待の口実に使われることや懲らしめ、戒めるという強力な権利であるとの印象を与え、体罰の正当化の根拠となってしまっていました。そこで改正後民法821条で親権者は子の人格を尊重し、子の年齢や発達程度に配慮しなければならなず、かつ、体罰等の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとしました。また、社会的に許容される正当なしつけは、820条の「監護及び教育」で行うことができるとされています。
嫡出推定制度の見直し
嫡出推定制度とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定すると規定したものです。
しかし、この規定により、離婚をしていても嫡出推定期間内(離婚後300日以内)に生まれた子は前夫の子と扱われるため、母親が出生届を提出せず、その結果、子は無国籍者となっていました。
従前の民法733条では、離婚後100日間(父親の推定重複を避けるため)の再婚を禁止していました(再婚禁止期間)。しかし、前述のような事態が問題視され、嫡出推定規定の見直しが行われました。改正後民法772条では「女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれた子についても、同様(妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する、同条一項前段)とする」とされ、その結果、民法733条の再婚禁止期間が廃止されました。
民事訴訟法の改正について
令和6年3月1日に民事訴訟法の一部が改正されました。以下では改正される規定のうち口頭弁論について説明していきます。
口頭弁論をウェブ会議で参加
民事訴訟において公開の法廷で行われる「口頭弁論」がウェブ会議で参加できるようになりました。
裁判所が当事者の意見を聞いて相当と認めたときは、当事者は裁判所に出頭せずにウェブ会議での参加を希望することができます。
既に「弁論準備手続」や「和解期日」などについてはウェブ会議(映像と音声付の方法)や電話会議ができるようになっていますが、「口頭弁論」の場合、法廷にモニターを設置し映像の送受信のみとなります。カメラ機能を有効にした状態での参加です。また、法廷の傍聴席ではモニター越しのやり取りを傍聴することが出来ます。
まとめ
以上が春に改正される法律についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。
相続登記が申請義務化となりました!
・不動産(土地・建物)を相続で取得した人(相続人)は相続したことを知った日 から3年以内に登記をしなければなりません。
相続登記の義務を履行しなかったら?
・正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性 があります。
相続人申告登記が新設されました!
・相続登記の申請義務の履行を簡易な方法でできる新たな登記です。
どのように申請するの?
・登記官に相続人が相続の開始と自らが相続人であることを申出て、当該相続人の戸籍 謄本を提出します。
民法改正で「懲戒権」が削除されました!
・民法821条で子の人格を尊重し、体罰の禁止が明記されました。
嫡出推定制度の見直しがされました!
・女性の再婚禁止期間がなくなり、嫡出推定期間で解釈が変わりました。
口頭弁論がウェブ会議で参加できるようになりました!
・法廷にモニターが設置され、ウェブ会議((映像と音声付の方法)での参加が可能に なり、これまで通り傍聴席で傍聴もできます。
この記事の監修者
代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。
その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。
モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。
<保有資格>
・宅地取引主任者(2004年取得)
・貸金業務取扱主任者(20009年取得)
・司法書士(2009年取得)
・行政書士(2010年取得)
<所属法人>
・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員
・行政書士法人やなぎグループ 代表社員
・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
・桜ことのは日本語学院 代表理事
・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください
当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。
<相談場所>
・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)
・弊所東京事務所(アクセスはこちら)
・オンライン相談
<相談対応>
・平日9:00〜20:00
・土日祝も対応(10:00〜18:00)
・事前の予約で出張対応も可能
私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
お問い合わせ先
相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
<お電話>
フリーダイヤル 0120-021-462
受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00
<メール>
受付時間 24時間受付中
2024.04.12 司法書士, 嫡出推定制度, 相続人申告登記, 相続登記の申請義務化, 行政書士
司法書士って何?どんな仕事?何をしてくれるの?
法律に関するお悩みをお持ちの方がインターネットを検索すると弁護士や司法書士のホームページがよく見受けられると思います。しかし、「弁護士と司法書士はどう違うの?」や「司法書士は何をしてくれるの?」という疑問を持たれる方もおられると思います。今回は司法書士の業務・弁護士等の専門家の違いについて説明していきます。司法書士について知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
司法書士は何をしてくれるの?
司法書士の業務は多岐にわたります。以下では司法書士が行う主要な業務について説明していきます。これから司法書士に依頼される方の参考にしていただけると幸いです。
登記または供託に関する手続
不動産の登記は、不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を表すことで、その不動産の所有者を示したり、住宅ローンを貸し付けている金融機関が自らの権利を確保したりします。
登記所に記録することで、その記録に関する証明書等を請求し、記録の内容を登記所にて誰でも確認することができます。
その不動産の所有者を示すためには、登記申請の手続をしなければなりません。
司法書士は、対象となる不動産、契約関係、不動産の所有者、契約する意思の確認などを行い、正しい登記を実現させるための業務を行っています。
こんなときはご相談ください ・住宅ローンを完済したが手続きがわからない
・故人名義の不動産の名義変更をしたい
司法書士は、会社の設立から役員変更、本店移転、商号変更、目的変更等の登記申請書ほか、必要書類の作成や登記申請手続を代理で行います。
これらは、司法書士の独占業務となり、登記だけではなく中小企業の法的課題において、その企業に助言を行う、企業法務に関する業務も行っています。
会社・法人の登記や企業法務については、会社・法人登記専門の司法書士に相談すると良いでしょう。
こんなときはご相談ください ・会社を設立したい
・役員の変更をしたい
・本店を移転したい
また、ある財産を国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることによって、一定の法律上の目的を果たすことも可能です。
例えば、家主から家賃の値上げを要求され、いままでの家賃額では受け取ってくれないような場合、借主は家賃を供託所に供託することによって、争いが解決するまでは家賃を支払ったことと同じ扱いにすることができます。
このような供託に関する手続を代理することも司法書士の業務とされています。
こんなときはご相談ください ・家主から家賃の値上げを要求された
裁判所に関する手続
司法書士は、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成することができます。
また、認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)であれば、代理人として簡易裁判所を管轄とする民事紛争においての、法廷での弁論や、様々な裁判上の手続を行うことができます。また、民事のトラブルについて相手方と裁判外で和解の交渉をすることもできます。
こんなときはご相談ください ・相続放棄をしたい
・後見等開始申立をしたい
・訴訟の代理(140万円以下)をしてほしい
・自分で訴訟をするので書類作成のサポートをお願いしたい
・借金の返済に困っている
その他
相続
相続が発生すると、不動産の名義変更、預貯金や株式などの払戻しや名義変更をする必要があり、自筆で書かれた遺言書の場合は裁判所での検認手続など、煩雑な手続を多く行わなければなりません。
手続が分かりにくい場合や忙しくて時間が取れない場合は、司法書士が代理で手続きを行います。
こんなときはご相談ください ・戸籍の読み方・集め方がわからない
・銀行解約の方法がわからない
・株式の相続手続きがわからない
・忙しくて相続手続きができない
生前対策
遺言書は、自分の死後に財産を誰にどの様に残したいかなど、最後の意思を法律に従って残すものです。
自筆証書遺言・公正証書遺言等、遺言書の作成方法はいくつかあり、選ぶことができます。司法書士は的確にアドバイスし、本人の最後の意思を形にする手助けが出来ます。
また、判断能力の減退や欠けた状態にある人々は、様々な意思決定を自ら行うことが困難となり、ひとりでは安心な生活をおくることができません。
その為、このような人々を法的に支援するための、成年後見制度というものもあります。
多くの司法書士がこの成年後見制度に携わっています。
民事信託は、信頼できる人に財産の名義を移して財産の管理や活用、そして処分を託する制度です。
その中でも、家族の民事信託は、「高齢者や障害を持つ人の生活などの支援のため」に活用され、財産の承継についても民事信託を活用することができます。
遺言、贈与、委任、成年後見制度等、他の方法との違いを理解して、民事信託を利用するかどうかを検討することが重要です。場合よっては、他の方法との併用を検討する必要があります。
遺言書作成、贈与や委任の書類作成・登記、成年後見制度に精通している司法書士に民事信託についても相談すると良いでしょう。
こんなときはご相談ください ・不動産を生前贈与したい
・遺言書を作成したい
・老後の財産管理が心配
・認知症対策をしたい
司法書士はどうすればなれるの?
・司法書士試験に合格した者
・裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事 した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経 験を有する者
・司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力 を有すると認められた者
上記の者が、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けることにより、司法書士となることができます。
司法書士はどんな試験?
司法書士の資格を得る為には、以下のような手順で進めていきます。
➀4月・5月 願書配布・出願
受験資格
年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できる
出願期間
例年5月中旬から下旬
願書提出
受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課へ郵送または持参
➁7月 筆記試験
※第1日曜日
午前の部
試験時間:9:30~11:30
試験形式:択一式(マークシート)
試験科目:憲法/民法/商法/刑法 合計35問(105点満点)
午後の部
試験時間:13:00~16:00
試験形式:択一式(マークシート)/記述式
試験科目:択一式
不動産登記法/商業登記法/民事訴訟法・民事執行法・民事保全法/供託法/司法書士法 合計35問(105点満点)
記述式
不動産登記法書式
商業登記法書式
各1問(140点満点)
※記述式問題とは、登記申請書の記載事項や判断理由等を問う問題です。
※令和6年度試験より、記述式問題の配点が70点満点から140点満点へ変更となります。
③10月 筆記試験合格発表・口述試験
試験形式:口述式
試験科目 不動産登記法/商業登記法/司法書士法(司法書士の業務を行うに必要な一般常識)
所要時間:1人あたり15分程度
受験地の法務局・地方法務局で掲示されるほか、法務省のホームページにも掲載されます。また、合格者には郵送にて通知されます。この通知書は口述試験の受験票となります。
④11月 最終合格発表
合格者は官報に公告されるほか、筆記試験の管轄法務局・地方法務局、法務省のホームページで掲示されます。
認定司法書士になるには?
認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件の訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等について,代理業務を行うことができる司法書士のことです (簡裁訴訟代理等関係業務)。
特別な研修を受け、考査により認定を受けた司法書士が、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。
認定司法書士の要件としては、以下3点です。
➀日本司法書士会連合会が実施する研修の課程を修了した者
➁認定考査の結果、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者
③司法書士会の会員であること
弁護士等の専門家の違い
いろいろな専門家がいてどの専門家が何ができて、何が得意なのかわからないという方も多いと思います。以下では弁護士等の専門家の違いについて説明していきます。
弁護士との違い
弁護士の業務は弁護士法で規定されており、司法書士も簡易裁判の代理人になることができますが、本来は弁護士の独占業務でした。現在も簡易裁判以外の民事訴訟や刑事事件の代理人は弁護士でなければできません。
また、弁護士は司法書士にも可能な、登記手続きの代理を含む法律事務全般も取り扱うことができます。その他にも遺産分割や離婚の調停などにおいて弁護士は相談や代理などできることに制限はありませんが、司法書士は一部制限があることがあります。
スキルや経験的に実際に業務が可能かは別にして、法律上は弁護士のほうができることが多くなります。
行政書士との違い
行政書士の業務は行政書士法で規定されています。
行政書士はおもに、国や都道府県、市町村などの行政機関への書類の作成や提出を代行して行うことのできる資格です。司法書士は法務局や裁判所への提出書類が対象となります。
行政機関向けの書類としては、官公庁への各種許認可や補助金などの申請、権利義務の証明書類が含まれます。行政書士は商業登記や不動産登記の書類作成や申請代行はできません。
上記のように、違いはありますが、相続や定款の作成など、司法書士と行政書士のどちらでも対応できる業務もあります。中には両方の資格を取り、業務の幅を広げている人もいます。
まとめ
以上が司法書士の業務・弁護士等の専門家の違いについてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。
司法書士は何をしてくれるの? ・登記または供託に関する手続 ・会社の設立から役員変更、本店移転、商号変更、目的変更等の登記申請書ほか、必要書類の作成や登記申請手続を代理で行う
・国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることができる
・裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成することが可能
・認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)であれば、代理人として簡易裁判所を管轄とする民事紛争においての、法廷での弁論や、様々な裁判上の手続を行うことが可能
・相続が発生した後の、不動産の名義変更、預貯金や株式などの払戻しや名義変更を代理で行う
・自筆証書遺言・公正証書遺言等、遺言書の作成方法のアドバイスが可能
・成年後見、贈与、信託の手続き
司法書士はどうすればなれるの? ・司法書士試験に合格した者 ・裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者
・司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められた者
弁護士等の専門家の違い ・簡易裁判以外の民事訴訟や刑事事件の代理人は弁護士の範囲 ・司法書士は簡易裁判での代理は可能(一定の制約あり)
・遺産分割や離婚の調停などにおいて弁護士は相談や代理などできることに制限はないが、司法書士は一部制限がある


相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結
- HOME
- ブログ
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
2025年 (1)
2024年 (11)
2023年 (51)
2022年 (67)
2021年 (55)
2020年 (48)
2019年 (13)
2018年 (28)
2017年 (24)
2016年 (26)
2015年 (13)
2014年 (13)
2013年 (11)
2012年 (9)